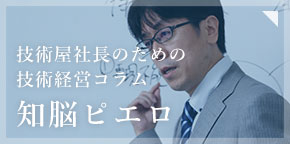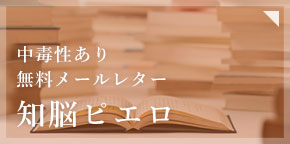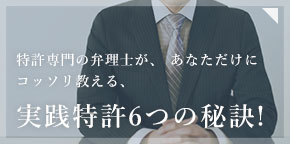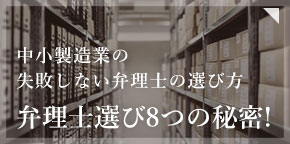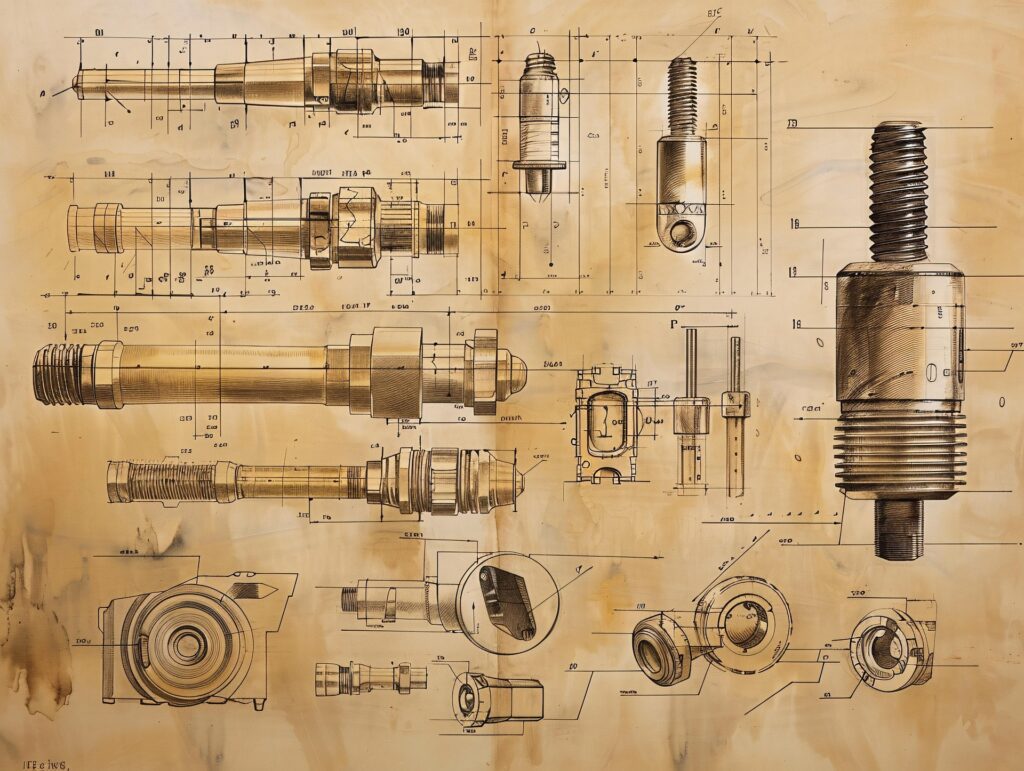
今回は、「知財×人事評価制度」について
お話ししていきましょう(^o^)
中小製造業では、
そもそも“人事評価制度”そのものが
整っていない会社も多いですよね(・o・)
でも、だからといって、
「評価制度ができていないから」
を理由に、
知財評価を後回しにしてしまうと、
せっかく育ち始めた“創造の芽”が
育ちません(>_<)
ですので、まずは人事制度全体を
完璧に整える前に、
「知財評価項目」から先に運用していく
というアプローチがおすすめです(^_^)b
◆ 社長の覚悟がすべての起点
最初に必要なのは
“制度”よりも“覚悟”です(・o・)
知財を重視してこなかった会社ほど、
「他社と違うことをやる」
という意識が弱くなりがちです(>_<)
まずは社長自身が、
「自社の“違い”をつくる」と決意して
その姿勢を明確に見せることが大切です。
“違い”を作るとは、
正解のない道を進み、
正解を創造していくということ。
誹謗・中傷・不安・恐怖と
戦う覚悟が必要になります(`´)
だからこそ、社長が
「知財創造宣言」を行い、
社員に向けて理念と覚悟を発信する。
これがスタートラインです(^_^)v
◆ “違い”→“知財”→“理財”の経営サイクル
(1) 違い(Differentiation)
他社と違う価値を生み出す挑戦。
(2) 知財(Intellectual Property)
その“違い”を形にし、守る仕組みを作る。
(3) 理財(Financial Value)
知財を利益に変え、社員に還元する。
この3段階が回り出すと、
“創造→保護→収益化”という
企業の知的循環が生まれます\(^_^)/
◆ 知財評価項目を先行して運用する
まずは、人事制度より一歩先に、
「知財を含む“違い創造活動”」を
評価対象として動かしてみましょう(^○^)
たとえば、こんな項目が考えられます。
(1) “違い”アイデア・改善提案の提出数
現場の工夫や発想を記録し、
「違い宝ノート」や「ひらめきBOX」で共有。
(2) 意匠・商標・発明への貢献度
出願だけでなく、情報提供や試作協力など、
“関わり方”全体を評価。
(3) “違い資産”の棚卸し・整理への参加
自社の強みや差別化要素を洗い出し、
一覧化・可視化する活動を評価。
(4) 他社の“違い資産”の分析・比較活動
同業他社の強みを調査し、
自社との比較表を作るプロジェクトへの参加。
(5) “違いロードマップ”作成への参画
自社の未来の差別化方針を描く会議や提案。
(6) 知的学び・共有姿勢
社内勉強会やアイデア会議への参加・貢献度。
これらの項目を回すことで、
“知財”という言葉の枠を超えた、
「違いを見つけ・育て・共有する文化」
が芽生えていきます(^_^)b
◆ 秘訣は「本気の見せ方」
制度を作るだけではダメです。
「また社長が変なことを始めた」と
思われてフェードアウトします(>_<)
ですので、
社長が「知財創造宣言」を行い、
決意を言葉と行動で示しましょう(`ε´)
さらに、称賛・表彰に加えて、
ボーナスなど収入に反映させる
仕組みを取り入れると、
社員の本気が早く芽吹きます(^_^)v
◆ まとめ
知財評価制度とは、
単なる“評価の項目追加”ではなく、
経営理念の実践形d(^_^o)
“違い”→“知財”→“理財”の流れを
社長自らが体現することこそ、
中小製造業の未来を
切り開くカギですp(^_^)q
続きはまた次回。
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・知財評価は“違い創造文化”の第一歩!
・社長の覚悟と宣言がすべての起点!
・称賛+報酬で社員の本気スイッチON!
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ