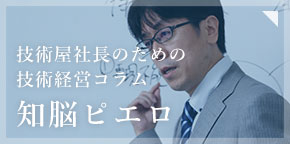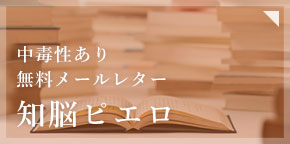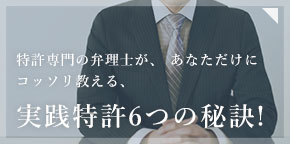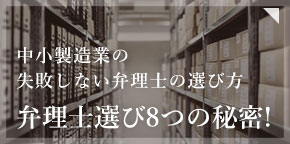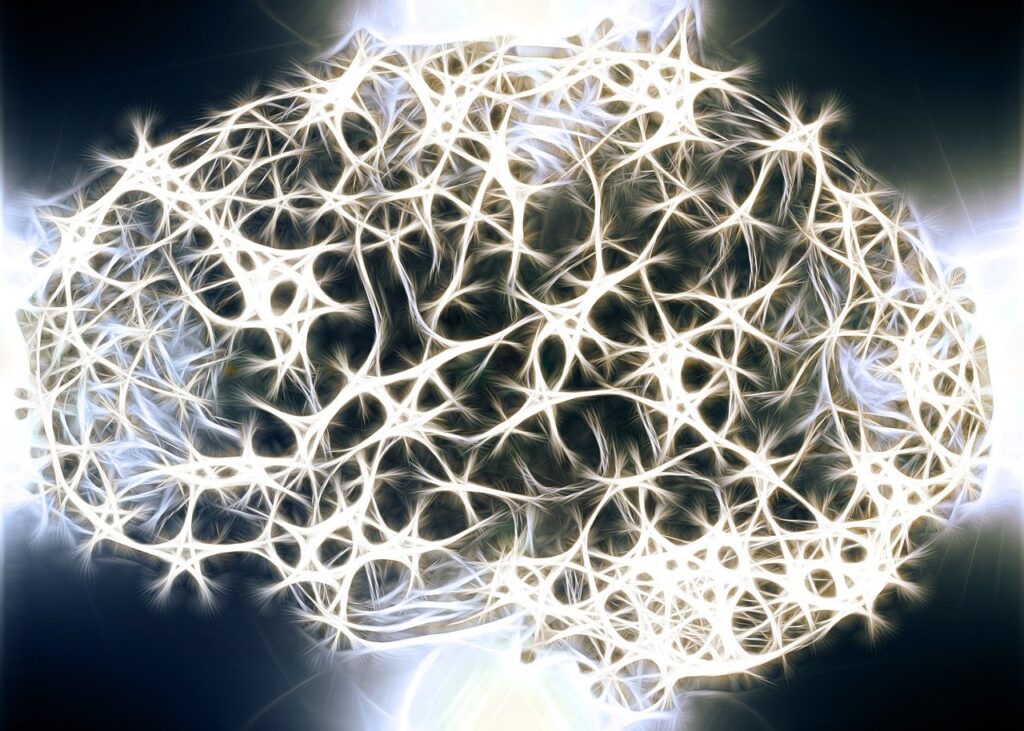
今回は話題の「AI設計ツール」について、
知財の視点からご紹介します(^○^)
いまやCADやCAEもAIで自動化され、
構造設計や応力計算、デザイン提案まで
AIが支援する時代になりましたね(^_^)v
「でも、AIが考えたものって、特許にできるの?」
「うちの社員が使った場合、
その成果物の権利ってどうなる?」
そんな疑問を持つ方も多いはず(^_^)b
◆ AIが設計したものは、誰のもの?
まず基本的に、
現状の日本の法律では、
AIそのものは発明者になりません。
でも、AIツールを使って設計した場合、
その操作や指示を出した人が、
“発明者”や“創作者”として
認められる可能性が高いですね(^○^)
つまり、社員がAI設計ツールを使って
生み出した成果は、
通常、その社員を通して、
会社に帰属させることが可能です(^-^)
ただし、そのためには、
・就業規則での職務発明規定
・成果物の帰属に関する契約
など、
社内ルールの整備が必須ですよ(^_^)v
◆ ノウハウとして残す?特許にする?
AIによる設計結果は、
出力プロセスも含めて非常に高度です。
特許で守ると
公開されるというリスクがあるため、
・出力条件やコツは社内ノウハウに
・構造や形状のポイントだけを特許に
というハイブリッドな活用が
おすすめですね。
つまり、外部から見え易い部分だけ、
マネされやすい部分だけを
特許化するということ(@_@)
また、AI設計で得られる知見は
単なる技術情報にとどまらず、
「なぜこの形状がベストなのか」など、
顧客説明や提案資料でも活躍します。
営業部門と設計部門の連携強化にも
つながる知財資源といえるでしょう(^-^)
さらに、AIを活用した設計プロセス自体を、
自社の標準手順や教育プログラムとして
体系化する動きも見られます(@_@)
こうした蓄積は、単なる技術ノウハウに
とどまらず、「知財的資産」として
会社の持続的成長を支える力になりますよp(^_^)q
他社が簡単に真似できない独自性として、
社内外にアピールしていきましょう(^_^)v
◆ “うちはまだ関係ない” では済まない時代
AI設計ツールは今後ますます普及し、
設計部門の効率化と共に、
発明の“質と量”が激変していきます(・o・)
中小企業でも使いやすいツールが増え、
競合他社との開発スピード競争も
加速していくことが予想されますよね(^_^)b
だからこそ、
「AIツールによる発明・設計をどう扱うか?」
という視点は、
今から持っておく必要があります(^-^)
さらに、AI設計による技術的な違いを
“自社ならではの強み”として
外部にアピールすることも重要です(^o^)
例えば、補助金申請や融資の審査でも、
「AI活用×知財戦略」という体制は
将来性や再現性の証明材料になりますね。
それでは、次回もお楽しみに。
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・AIの操作側=発明者になる!
・出力内容の扱い方を戦略的に!
・就業規則と契約で社内整備を!
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ