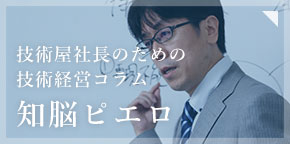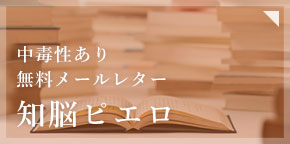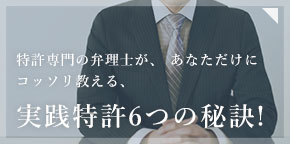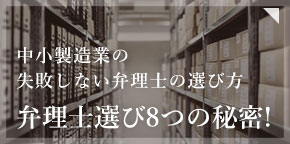今回は、
「知財×社員教育の仕組み化」
について、
お話ししていきましょう(^o^)
以前、知財を通じて
“技術者の誇り”を育てる、
というお話をしました(^_^)b
今回は、その誇りを“仕組み”として
会社に定着させる方法です。
◆「仕組み化」ってなに?
せっかく社員が知財に関心を持っても、
その場限りの話で終わってしまうと
もったいないですよね(>_<)
たとえば、こうした悩みをよく聞きます。
「知財の勉強会をやったけど続かない」
「発明は出てくるけど制度がなくて申請されない」
大事なのは、“偶然の創造”を
“習慣的な創造”に変える
仕組みを作ること(^_^)v
◆ ステップ1:場をつくる
まずは、社員が気軽に
アイデアを出せる場を
会社として用意することですp(^_^)q
・毎月1回の「改善アイデア会議」
・朝礼での「発明ミニ発表」
・匿名投稿できる「ひらめきBOX」
どんな形でも構いません。
ポイントは、“発想すること”を
日常にすることです(^○^)
◆ ステップ2:見える化する
次に、提出されたアイデアを
社内で“見える化”しましょう。
・壁や掲示板に「今月のアイデアTOP3」
・採用された工夫を写真付きで掲示
・「社内特許リスト」を共有フォルダで管理
「自分の発想が会社に残った」
と実感できると、
社員のモチベーションは
一気に上がりますよ(@_@)
◆ ステップ3:評価と称賛を仕組みに
せっかくのアイデアも、
評価が曖昧だと続きません。
・年1回「知財アワード」を開催
・採用アイデアには表彰や金一封
・発明者の名前を特許に記載して公表
称賛は最大の教育です(^_^)b
「努力が認められた」という実感こそ、
知財を“自分ごと化”する
最大のカギになります(^_^)v
◆ ステップ4:専門家を巻き込む
発明や商標の判断は
難しい部分もあります(°°)
社内で迷ったら、
弁理士などの専門家を
“顧問的に”関わらせるのもおすすめ。
「社外の先生に聞ける安心感」が
社員の挑戦を後押しします(^○^)
◆ ステップ5:継続するための制度設計
仕組みを作っても、
1年で終わってしまう会社が多いです(>_<)
続けるコツは、
“経営目標と結びつける”こと。
たとえば、
「年3件の特許出願を目指す」
「改善提案を営業ツール化する」
数値や目的を明確にすると、
知財活動が経営活動の
一部として根付きます(^_^)v
◆ まとめ
知財教育のゴールは、
社員が“自分の発想に
誇りを持つ文化”を育てること。
・場をつくり
・見える化し
・称賛し
・専門家を活かし
・継続させる
この5つを社内制度として回せば、
知財は“知の財産”から
“組織の文化”へと
進化していきます\(^_^)/
誇りが文化になれば、
その会社は必ず強くなります。
続きはまた次回。
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・知財教育は“誇りの仕組み化”から!
・場づくり・見える化・称賛の三本柱!
・知財活動を経営目標とつなげて継続!
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ