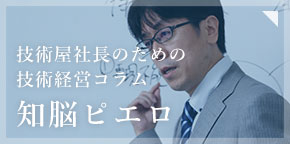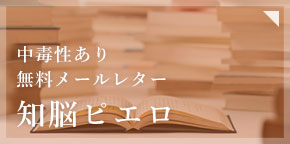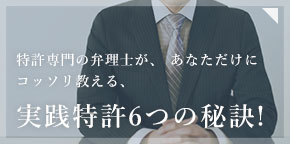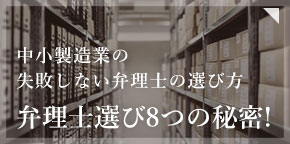今回は、知財のお話しです(^^)
最近は、他社、大学など、
いろんな外部の企業や組織と組んで
モノづくりを進める機会が
増えてますよね(^o^)
でも、そこで注意したいのが…
「その発明、いったい誰のもの?」問題!
今回は、共同開発のときに
モメないようにするための、
知財トラブル防止術を
お届けしましょうd(^_^o)
◆ あるある!共同開発のトラブル例
例えば、こんな例があり得ます(^_^)b
・ 開発がうまくいったと思ったら、
相手側が特許出願していた!
・ 仕様を共有したら、
勝手に改良されて
自社が蚊帳の外に置かれていた
・ 費用はうち持ちなのに、
権利は相手企業の名義に…
このように、技術は共有できても、
“気持ち”は共有されていなかった!
…なんてこと、
起こる可能性がありますね(>_<)
◆ 基本の考え方:「誰が発明したか」
基本的に、特許を取ることができるのは、
発明をした人です!(^^)!
または、発明をした人から、
特許を取る権利を譲り受けた人です。
一般的には、発明をした人が属する会社が、
会社名で特許を取ることが多いですよね。
例え会社名で特許を取るにしても、
まずは誰が発明したのか、ということは、
非常に重要です(^o^)
発明者として記載されることになりますからね。
では、発明者とは誰か?
そんなの簡単じゃない?と思うかもしれないけど、
特に、共同開発の場合、
この辺が曖昧になりがちですね(>o<)
基本型は、
「発明者=実際に発明した人」
です(`´)
“技術的アイデアを出した人”が
発明者として記録されますφ(.. )
なので、お金を出した人とか、
指示を受けて単に測定した人とかは、
普通は発明者にはなりません(^_^)b
でも実際には、
開発を“支えた人”の貢献が
大きいこともありますよね。
だからこそ、事前の話し合いと合意が
大切になってきますよd(^_^o)
◆ モメないようにするためのルール
・ 共同開発契約を結ぶこと
→ 知財の帰属、出願名義、利用条件などを
文書で明確にしておきましょうφ(.. )
・ 秘密保持契約(NDA)は必須です
→ 話す前に締結!が鉄則。
特許出願前の情報漏れ防止にも
効果的ですね(^o^)
・ 共同出願?単独出願?を決めておこう
→ モヤモヤするのは“曖昧”な状態。
話し合ってはっきり決めておきましょう(^_^)b
◆ トラブル回避のための工夫も!
あとになって揉めるときは、
取り決めなどが不明確であることがほとんど。
ですので、例えば、こんな工夫があり得ます。
・ 会議の議事録を残す
・ 技術提案の出所を記録する
・ メール・チャットはフォルダ保存
“あとで言った・言わない”にならないよう、
客観的な証拠を残すクセが大切ですね。
◆ そもそも、「発明」じゃなくても…
商品名、外観デザイン、キャッチコピーなど、
“発明”じゃなくても知財はあり得ます(・o・)
こちらも忘れずに話し合いましょう。
「気づいたら相手が商標出してた…」
なんてことも、あり得る話しです(>_<)
共同開発はチャンスの宝庫ですが、
トラブルが起きてからでは遅いですよね。
「お金」と「アイデア」だけでなく、
「気持ち」もフェアに分け合う仕組みを
最初に整えておきましょう(^-^)
それでは、次回もお楽しみに。
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・知財は出す前にルールを決めよう!
・共同開発契約とNDAは必須アイテム!
・話し合いと記録がトラブル防止のカギ!
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ